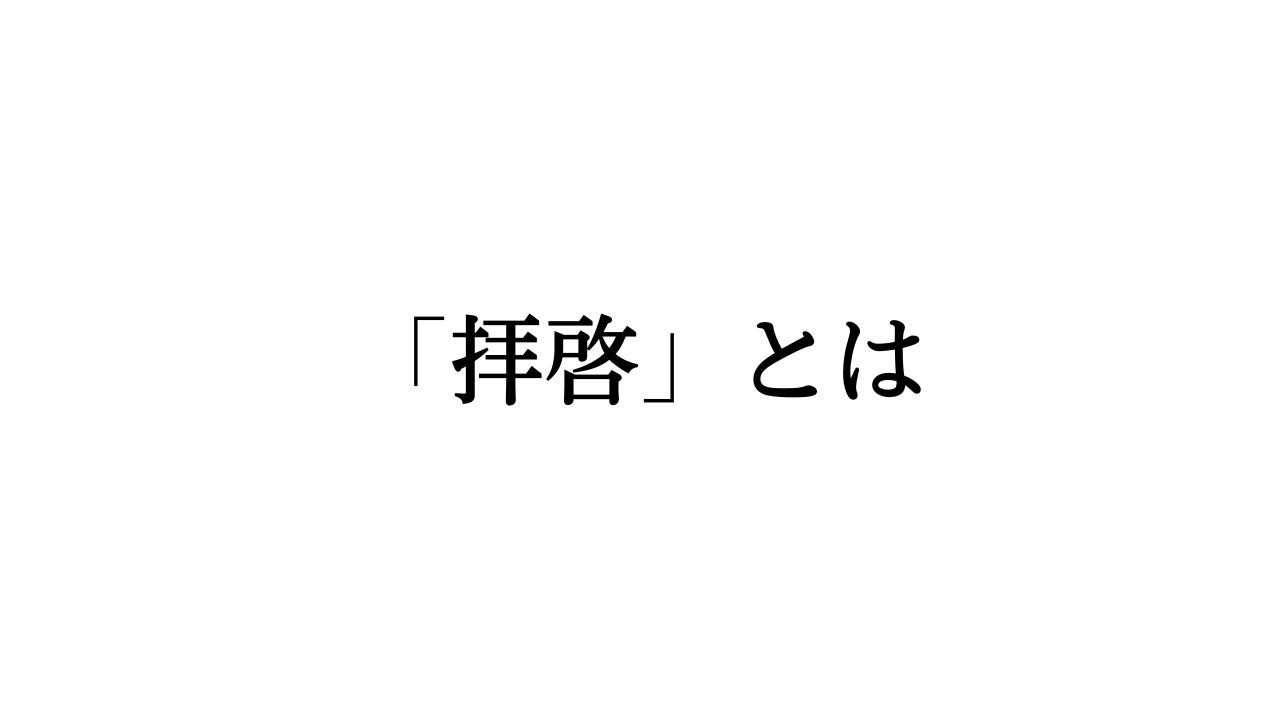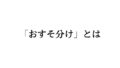「拝啓」という言葉、正しく使えていますか?
ビジネス文書やフォーマルな手紙を書くとき、「拝啓」を使うのが一般的ですが、実は誤った使い方をしている人も少なくありません。
この記事では、「拝啓」の意味や正しい使い方、時候の挨拶との関係、さらに「前略」「謹啓」との違いまで詳しく解説します。
手紙のマナーをしっかり押さえて、相手に好印象を与える文章を書けるようになりましょう。
フォーマルな手紙を書く機会がある方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。
拝啓とは?意味や使い方を解説
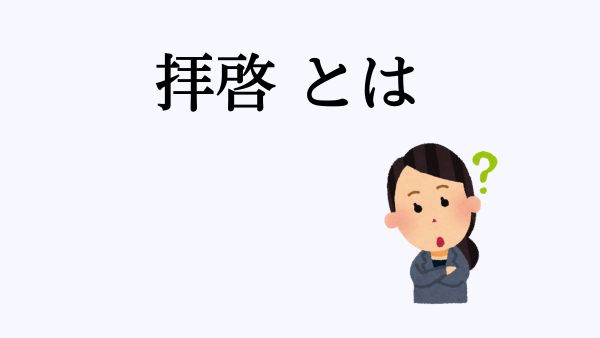
「拝啓」という言葉の意味や使い方について詳しく解説します。
それでは、順番に見ていきましょう。
① 拝啓の意味とは?
「拝啓」は、手紙や文章の冒頭で使う敬語表現です。「拝」という字には「深く敬意を払う」という意味があり、「啓」は「申し上げる」という意味を持ちます。つまり、「拝啓」は「謹んで申し上げます」という意味になります。
これは、相手に対して敬意を示しながら、手紙の本文を始める際の挨拶として使われます。特にビジネスやフォーマルな場面で使われることが多いですね。
例えば、上司や取引先、目上の人に対して手紙を書く場合、「拝啓」を用いることで礼儀正しい印象を与えることができます。
ただし、これは主に手紙や文書で使う表現であり、日常会話では使われません。
② どんな場面で使うのか?
「拝啓」は、正式な手紙やビジネス文書の冒頭で使われます。具体的には以下のような場面で使用されます。
- 取引先や上司への報告書や依頼文
- フォーマルな挨拶状や招待状
- 就職活動での手紙やお礼状
- 目上の人への感謝やお詫びの手紙
このように、相手に対して敬意を示す必要がある場面で使うのが一般的です。
一方で、カジュアルなメールやLINEなどのメッセージではほとんど使われません。親しい人に対する手紙では、「こんにちは」「お元気ですか?」などのフランクな挨拶の方が適しています。
③ 拝啓を使うときのルール
「拝啓」を使う際には、いくつかのルールがあります。主なポイントは以下の通りです。
- 「拝啓」の後には「時候の挨拶」を入れる
- 手紙の最後には「敬具」をセットで使う
- カジュアルな手紙には適さない
- 相手との関係性に応じて適切な表現を選ぶ
例えば、「拝啓」の後には、「春の訪れを感じる今日この頃、皆様におかれましては…」といった時候の挨拶を入れるのが一般的です。
また、「拝啓」を使ったら、手紙の最後には必ず「敬具」で結ぶのが基本ルールです。これは、「拝啓」が手紙の始まりの挨拶であるのに対し、「敬具」は結びの挨拶として対応しているからです。
④ 使わない方がいい場合もある?
「拝啓」はフォーマルな場面で使われる表現ですが、すべての手紙に適しているわけではありません。以下のような場合には、別の表現を使う方がよいでしょう。
- 親しい友人や家族への手紙
- メールやチャットなどのカジュアルなやり取り
- 急ぎの連絡や短文のメッセージ
例えば、親しい友人に手紙を書く場合、「拝啓」よりも「こんにちは」や「○○さん、お元気ですか?」のようなカジュアルな表現の方が適しています。
また、メールでは「拝啓」を使うとやや堅苦しい印象になるため、ビジネスメールでも「お世話になっております」や「はじめまして」といった表現を使うのが一般的です。
状況に応じて適切な表現を選ぶことが大切ですね。
拝啓の正しい書き方と例文
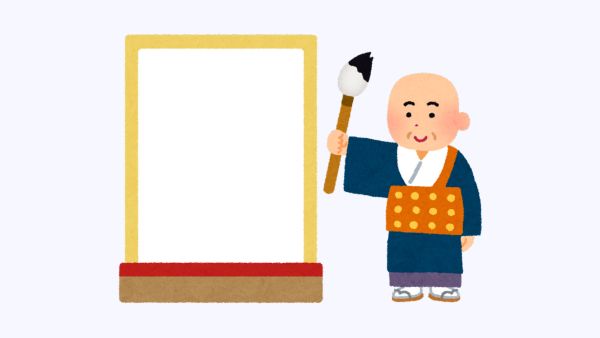
「拝啓」を使う際の基本的な書き方と、実際の例文を紹介します。
それでは、詳しく解説していきます。
① 手紙の冒頭に使う基本ルール
「拝啓」は、フォーマルな手紙の冒頭に使われる敬語表現です。基本的な使い方には以下のルールがあります。
- 手紙の冒頭に「拝啓」を書く
- 「拝啓」の後には時候の挨拶を入れる
- 本文を書き、最後に「敬具」などの結びの言葉を入れる
例えば、手紙の構成としては以下のようになります。
拝啓 〇〇の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 (本文) 敬具
このように、「拝啓」と「敬具」はセットで使うのが一般的です。
② 拝啓に続く「時候の挨拶」とは?
「拝啓」の後には、時候の挨拶を入れるのが基本です。時候の挨拶とは、季節に応じた挨拶文のことを指します。
例えば、以下のような表現が一般的です。
| 季節 | 時候の挨拶(例) |
|---|---|
| 春 | 「陽春の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。」 |
| 夏 | 「盛夏の候、皆様におかれましてはご健勝のことと存じます。」 |
| 秋 | 「秋涼の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。」 |
| 冬 | 「厳寒の候、皆様におかれましては益々ご健勝のことと存じます。」 |
このように、手紙を書く季節に応じた適切な表現を選ぶことが大切です。
③ 例文で見る「拝啓」の使い方
実際に「拝啓」を使った手紙の例文を紹介します。
例文①:ビジネスの挨拶状
拝啓 新緑の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、このたび弊社では新商品を発売する運びとなりました。 つきましては、ぜひご覧いただきたく、カタログを同封いたしましたのでご高覧賜りますようお願い申し上げます。 敬具
例文②:就職活動での礼状
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 先日は貴重なお時間を頂戴し、誠にありがとうございました。 〇〇様のご説明を伺い、貴社での業務内容についてより深く理解することができました。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 敬具
このように、「拝啓」を使うことで、フォーマルな手紙の印象を与えることができます。
④ ビジネスメールでの使用はOK?
「拝啓」は主に手紙で使う表現であり、ビジネスメールにはあまり適していません。メールの場合は、以下のような表現が一般的です。
- 「お世話になっております。」
- 「はじめまして、〇〇と申します。」
- 「いつもご愛顧いただきありがとうございます。」
ビジネスメールで「拝啓」を使うと、少し堅苦しい印象を与えてしまうことがあります。そのため、状況に応じて適切な表現を選ぶことが重要です。
拝啓と敬具のセットはなぜ必要?

「拝啓」と「敬具」はセットで使われるのが一般的ですが、その理由について詳しく解説します。
それでは、順番に見ていきましょう。
① 拝啓と敬具の関係とは?
「拝啓」と「敬具」は、正式な手紙の書き方においてセットで使われます。
「拝啓」は手紙の冒頭で用いられ、「相手に敬意を表しながら、ここから文章を始めます」という意味を持ちます。一方で、「敬具」は手紙の結びの部分に使われ、「謹んで申し上げました」という意味を持つ言葉です。
つまり、「拝啓」と「敬具」は、文章の始まりと終わりを整えるためのペアとなる表現なのです。
② なぜ「拝啓」だけではダメなのか?
手紙の書き方には、決まったマナーがあり、その中で「拝啓」と「敬具」は必ずセットで使用するのが基本ルールです。
「拝啓」だけを使ってしまうと、手紙の締めくくりが不自然になります。「拝啓」はあくまで手紙の始まりを示す言葉なので、最後には「敬具」などの結びの言葉を添えることで、文章全体のバランスが取れるのです。
例えば、「拝啓」のみを使い、最後に何も結びの言葉を入れないと、手紙の印象が中途半端になってしまいます。
③ 敬具以外に使える結びの言葉
「拝啓」とセットで使われるのは「敬具」だけではありません。手紙の内容や相手との関係によって、以下のような結びの言葉を使うこともあります。
| 結びの言葉 | 使用される場面 |
|---|---|
| 敬具 | 一般的なビジネス文書やフォーマルな手紙 |
| 敬白 | 目上の人や格式の高い手紙 |
| 謹白 | より丁寧な敬語表現 |
| かしこ | 女性が書く手紙の結び(親しい人向け) |
例えば、目上の人に対して手紙を書く場合、「敬具」よりも「敬白」や「謹白」を使う方が丁寧な印象を与えることができます。
④ 例文で理解する拝啓と敬具の流れ
「拝啓」と「敬具」を正しく使った例文を見てみましょう。
例文①:ビジネスの手紙
拝啓 春暖の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 さて、このたび弊社では新しい商品を発売いたしました。 詳細をお知らせいたしますので、ぜひご検討いただければ幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。 敬具
例文②:就職活動の礼状
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 先日は貴重なお時間を頂戴し、誠にありがとうございました。 貴社での業務内容について深く理解することができ、大変勉強になりました。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 敬具
このように、手紙の最初に「拝啓」を入れ、最後に「敬具」で締めることで、形式の整った文章になります。
拝啓と似た表現との違い

「拝啓」とよく似た表現がいくつかあります。それぞれの違いや使い分けについて詳しく解説します。
それでは、順番に見ていきましょう。
① 「前略」「謹啓」との違い
「拝啓」と似た表現として、「前略」や「謹啓」などがあります。それぞれの意味と使い方の違いを整理してみましょう。
| 表現 | 意味・用途 | 結びの言葉 |
|---|---|---|
| 拝啓 | 一般的な手紙の冒頭に使う敬語表現 | 敬具 |
| 謹啓 | 「拝啓」よりも丁寧で改まった表現 | 謹言・敬白 |
| 前略 | 時候の挨拶を省略し、用件をすぐに伝える際に使用 | 草々 |
「謹啓」は、特に目上の人に対する改まった手紙で使われます。結びの言葉としては「謹言」や「敬白」が適しています。
一方で、「前略」は時候の挨拶を省略する際に使い、用件を端的に伝える手紙に適しています。結びの言葉としては「草々」を用います。
② カジュアルな手紙では何を使う?
親しい人や友人に手紙を書く場合、「拝啓」のような格式張った表現はあまり使われません。その代わりに、以下のようなカジュアルな挨拶が適しています。
- 「こんにちは、○○さん」
- 「お元気ですか?」
- 「先日はありがとう!」
例えば、親しい友人に手紙を書く場合は、以下のような形になります。
○○さんへ 久しぶり!元気にしてる? この前の旅行の写真、送ってくれてありがとう。 とても楽しい時間だったね。 また近いうちに会おうね! ○○より
このように、カジュアルな手紙では、特に決まった形式はなく、自由な表現が可能です。
③ 改まった場面での適切な表現
フォーマルな場面では、「拝啓」や「謹啓」を使うのが一般的ですが、さらに丁寧な表現が求められる場合もあります。
例えば、結婚式の招待状や重要なビジネス文書では、「謹啓」や「恭敬」などの表現が使われます。
例文:結婚式の招待状
謹啓 晩秋の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 このたび、私たちは結婚する運びとなりました。 つきましては、ささやかながら披露宴を催したく、ご案内申し上げます。 謹言
このように、場面に応じた適切な表現を使うことで、相手に対して敬意を表すことができます。
④ 使い分けが大事なポイント
「拝啓」をはじめとする手紙の冒頭表現は、相手や状況に応じて適切に使い分けることが大切です。
まとめると、
- 「拝啓」 → 一般的なフォーマルな手紙
- 「謹啓」 → 目上の人へのより丁寧な手紙
- 「前略」 → 簡潔に用件を伝える手紙
- カジュアルな手紙 → 友人や親しい人への手紙
これらの違いをしっかり理解し、適切な表現を選ぶようにしましょう。
まとめ|拝啓の正しい使い方を覚えよう
この記事では、「拝啓」の意味や使い方、関連する表現との違いについて詳しく解説しました。
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 拝啓の意味とは? | 「拝啓」は、手紙の冒頭で使う敬語表現で、相手に敬意を示す意味を持つ。 |
| どんな場面で使うのか? | ビジネス文書やフォーマルな手紙で使用し、カジュアルなメールでは避ける。 |
| 拝啓を使うときのルール | 「拝啓」の後には時候の挨拶を入れ、手紙の最後には「敬具」を添える。 |
| 使わない方がいい場合 | 親しい友人や家族への手紙、カジュアルなメールでは「拝啓」は不要。 |
| 「前略」「謹啓」との違い | 「前略」は時候の挨拶を省略、「謹啓」はより丁寧な表現。 |
「拝啓」は手紙を書く際の基本となる表現ですが、適切な使い方を理解していないと、不自然な文章になってしまうこともあります。
大切なのは、「誰に」「どのような場面で」手紙を書くのかを意識し、それにふさわしい表現を選ぶことです。
もしフォーマルな手紙を書く機会があれば、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
適切な敬語表現を使うことで、より洗練された文章を書くことができるようになりますよ。